名古屋の経営戦略提案なら
ITO経営研究所(伊藤会計事務所)にお任せください。
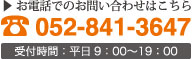

世界におけるレンタル業の第1号は電話の発明者グラハム・ベルが1887年に始めた「電話機の貸し出し」だそうですが、日本のレンタル業は江戸時代までさかのぼります。貸し出したものは「ふん...
明けましておめでとうございます。今年100周年を迎えるディズニーのミッションは「(中略)他に類を見ないストーリーテリングの力で、世界中の人々にエンターテインメント、情報、インスピレー...
とら年も残りわずかです。とら年は「新しく立ち上げる」「芽吹いたものが成長する」という年回りだそうです。この一年を振り返っていかがだったでしょうか。来年はうさぎ年です。大変なことがあ...
7月に発表された「世界人口推計2022年版」によれば、世界の人口は今年の11月15日に 80 億人に達し、来年 にはインドが中国を抜いて世界で最も人口が多い国になると予測されています。今この瞬間...
2022年のベストセラー小説である原田ひ香さんの『三千円の使いかた』はこんな風に始まります。「人は三千円の使い方で人生が決まるよ、と祖母は言った。え?三千円?何言っているの?」。本...
1977年9月3日。王貞治さんが本塁打世界最高記録を達成しました。猛練習の末に「1本足打法」を編み出し、当時のメジャーリーグ記録、ハンク・アーロンの755号本塁打を抜いて世界新記録を...
我が人生に悔いなし。常にそう思いながら生きたいものですが、雑誌『プレジデント』が2012年に行ったアンケートによれば、シニア世代が健康面で後悔していることの第1位は「歯の定期検診を...
今から100年前は「大正デモクラシー」や「大正ロマン」などの言葉が生まれた大正時代。大卒サラリーマンの初任給は50~60円。職業婦人の月給はタイピスト40円、電話交換手35円、事務員30円。純...
6月27日は「零細・中小企業デー」。小回りが利く零細・中小企業にはユニークな福利厚生があります。例えば、兵庫県で美容室を展開する「チカラコーポレーション」の「失恋休暇」。失恋を上司...
5月5日は端午の節句。現在のこいのぼりは合成繊維ですが、江戸時代は和紙に模様を手描きしていたそうです。数年前、手描きこいのぼりの伝統を一人で守って来た女性職人が引退されました。「伝...